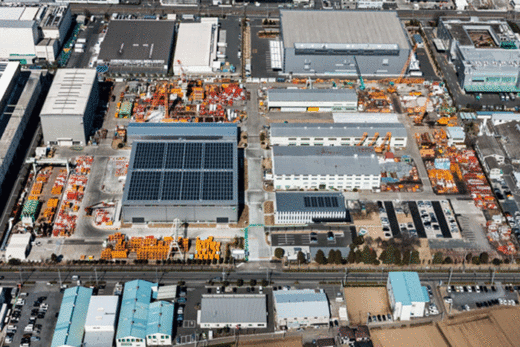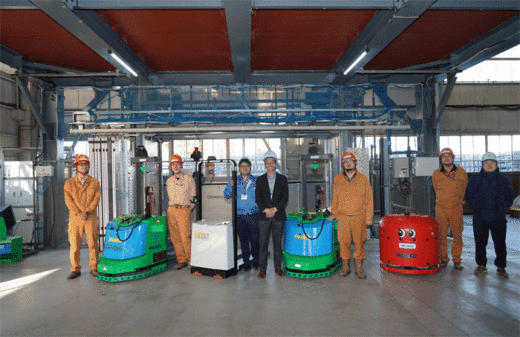大手ゼネコンの大林組がロボットによる建設現場自動化で、人手不足解消と生産性向上を目指した取り組みを始めている。埼玉県川越市にある東日本ロボティクスセンターでは、今年6月稼働を目指し、産業機器販売を始めとした商社事業から製造事業まで行うアルテックと共同で自律型搬送ロボットの開発を進行中だ。東日本ロボティクスセンターの赤井亮太所長は「建設現場での隙間時間の有効活用により、少しの人力で大きな効果を生み出すもの」とそのプロジェクトの趣旨を説明する。機器導入のプロジェクトを担当したアルテックの辻本茂浩課長とともに、その狙いと展望を聞いた。
<大林組 東日本ロボティクスセンター赤井亮太所長 兼施工技術部長>

建設現場の隙間時間を有効活用
日本のゼネコンと呼ばれる建設会社の1社である大林組。これまで著名な建築物やインフラ構築で数多くの実績を積み重ねている。その大林組でも現在、他の産業と同様かそれ以上に深刻な問題となっているのが人手不足だという。
大林組の東日本ロボティクスセンターの赤井亮太所長は「労働者がすでに足りない時代ですし、今後その傾向が益々拡大していくことがはっきりしている中で、我々は何を成すべきか考えねばなりません。建設現場での職人さんをはじめ、多くの作業員の採用・募集が厳しくなっています。仕事は多くありながら、それを受注しても人が集まらない。その課題解決を補うために、生まれたのがこの東日本ロボティクスセンターです」と話す。
東日本ロボティクスセンターは以前からあった東京機械工場から2019年4月に名称変更して誕生したものだ。建設現場で使用する工事機械や重機類の整備・改良・開発が主な任務に変わりはないが、名称変更には「プラスアルファとして省力化、省人化、自動化をキーワードにした要素が強くなり、開発系の業務が多くなった。その一環として、現場に自動化を目指すロボット導入を図る試みを進めている」と赤井所長は説明する。
そこで建設現場での省人化、省力化、自動化を考えた場合、課題として出ていたのが、建設と共に建設資材の運び込みを同時に行っている不合理性だった。建設現場では昼間は作業しているが、夜間は作業員が帰るため活動できない。そのため、昼間に行う作業の中で資材搬入作業も同時に行わなくてはならない。これを夜間に建設資材を運び込んでいれば、翌日朝から作業員が建設作業にすぐに取り掛かれる手はずとなる。「隙間時間の有効活用というか、作業効率の向上につながる」と赤井所長の話すように、これができれば、建設業界にとっては、大きな変革となる。
そこで出会ったのがアルテックの自律走行フォーク型搬送ロボットのStocklinだった。
<左から大林組東日本ロボティクスセンター運営管理部メカトロニクス課の森田一義副課長、同施工技術部建築機械課の佐藤匡則副課長、赤井所長、アルテック第2産業機械事業部物流システム営業部の辻本茂浩課長>
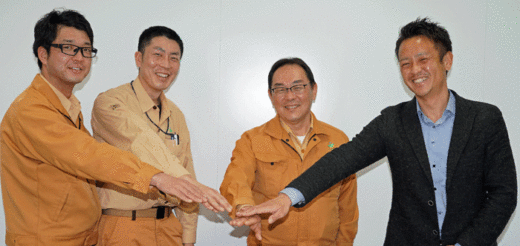
100㎏以上の積載荷重の要望に応えたStocklin
「大林組さんと出会ったのは3年前のロボデックス展でした。その時、将来の建設現場の方向性を伺ったときに、『建設資材を自動搬送したい』という要望を聞きました。それも100㎏以上の積載荷重が必要ということでした。当時展示していた自律型走行ロボットの積載荷重が小さかったため、その後世界中の自律型走行ロボットを調査・研究し、これだと思った『Stocklinロボット』を主体にプロジェクトの提案をさせてもらいました」とアルテックの辻本茂浩課長。
このStocklinとは、スイスのStocklin Logistik AGが開発した自律型走行ロボットで、水平面での荷積みから荷下ろしまでの輸送作業を行う自律走行フォーク型搬送ロボットだ。そのモデルの一つがEAGLE-ANT1で最大積載容量は1200㎏ある。この提案は大林組に採用され、2019年6月から専用ソフトウェア開発を含めたプロジェクトが始まり、12月からは現場導入に向けての各種実証試験段階に入っている。
大林組にその提案が評価された点を辻本課長は「建設現場で必要なのは、多層階での作業に使えるものでした。他の搬送ロボットを使用しても、多層階での使用には不向きで、エレベーターにも乗れないという基本的な問題がありました。それらをクリアしたのがStocklinでした」と語る。
大林組のプロジェクトチームの佐藤匡則副課長は「建設現場は雑多なヘビーデューティな環境で、磁気テープなどで動線を決めたりする必要がなく、場所も転々と変わる中での応用性の高さも優れていた点でした」と話す。
もう一つ大きな点は大林組が既製のロボットを導入するだけでなく、建設現場の状況に合わせた運行ソフト開発を進められたことだ。つまり、Stocklinを自由にカスタマイズできることだった。Stocklinにはブルーボテックスと呼ばれる基本ソフトがインストールされており、このソフトと開発した運行ソフトウェアをつなげることで、現場環境に応じた自由なカスタマイズが可能になる。様々な環境下の建設現場では、この運用ソフトは重要となる。
同プロジェクトの森田一義副課長は「現場で作業する人たちが簡単に操作できるものでないと、意味がありません。現場の運用に合わせてスケジュール管理できるソフトを独自に開発しています。現在、様々なパターンを試験し、6月の本格稼働に向けて調整中です」と話す。
実際、都内の超高層ビルの建設現場に持ち込み、23階までStocklinでの自動搬送を試したこともあるという。「1階で建設資材をピックアップし、エレベーターの中に乗り込み、資材を下ろし、エレベーターを抜け出し、エレベーターが23階に着くと、別のStocklinが資材をピックアップして、所定の場所に下ろす作業を繰り返し行いました」と辻本課長。こうした積み重ねにより、他社製品と比較して優位性を確立していったという。
<東日本ロボティクスセンターでの実験風景>
6月導入、結果は秋頃、物流現場にも生かす
このプロジェクトは実際に今年6月に都内のビル建築現場で稼働させ、秋ごろまでに各種データを集め、生産性の高さが実証されれば、今後あらゆる現場で稼働させる方針だ。それとともに、この東日本ロボティクスセンターの拡充も図っていくという。
赤井所長は「今後、Stocklinに限らず、様々な搬送ロボット、垂直揚陸機等の開発や改良、さらには建設現場が一変するような新しい取り組みを進めていきたい。例えば、建設現場で使用するパワークレーン等の自動運転なども、すでに試験段階だが進めている。AIによる画像認識で人とモノを判別する技術を建設現場に導入するとか、やることはいっぱいあります。それ自体は楽しいのですが、早くやらなければならないのがスピード時代の現実ですからね」と笑う。
また、大震災、大雨等の災害時に遠隔操作できる重機の開発もスピード感をもって開発を進めていくという。
一方、アルテックでは物流現場での自律型搬送ロボット採用も本格的になっているとし、今後力を入れていく予定だという。「私どもの部門は3つの部署で構成されており、自律型搬送ロボット、自動梱包、自動収納とあり、いずれも物流業界と密接ですので、企業や施設に適応した自律型搬送ロボットの取り組みなども紹介していきたい」と話す。
少子高齢化による人手不足が深刻な現在の日本の産業界だけに、様々な業界でロボットによる自動化が進められている。建設業界も物流業界と同様、やはり人手不足は深刻なようで、自動化の動きはゼネコンを中心として、活発に進められているようだ。特に、自動搬送ロボットについては、普及元年とも呼ばれるほど、熱を帯びてきている。大林組とアルテックの取り組みも多層階、エレベーターに乗り込める搬送ロボットの活用で、今後大型多層階の物流施設にも応用される技術となるだろう。今年秋ごろ出る予定の効率化のデータ集計が楽しみとなる。
取材:2020年3月18日 大林組東日本ロボティクスセンター
物流最前線/「Safety Driving Award 2024」 進化・深化する交通事故対策