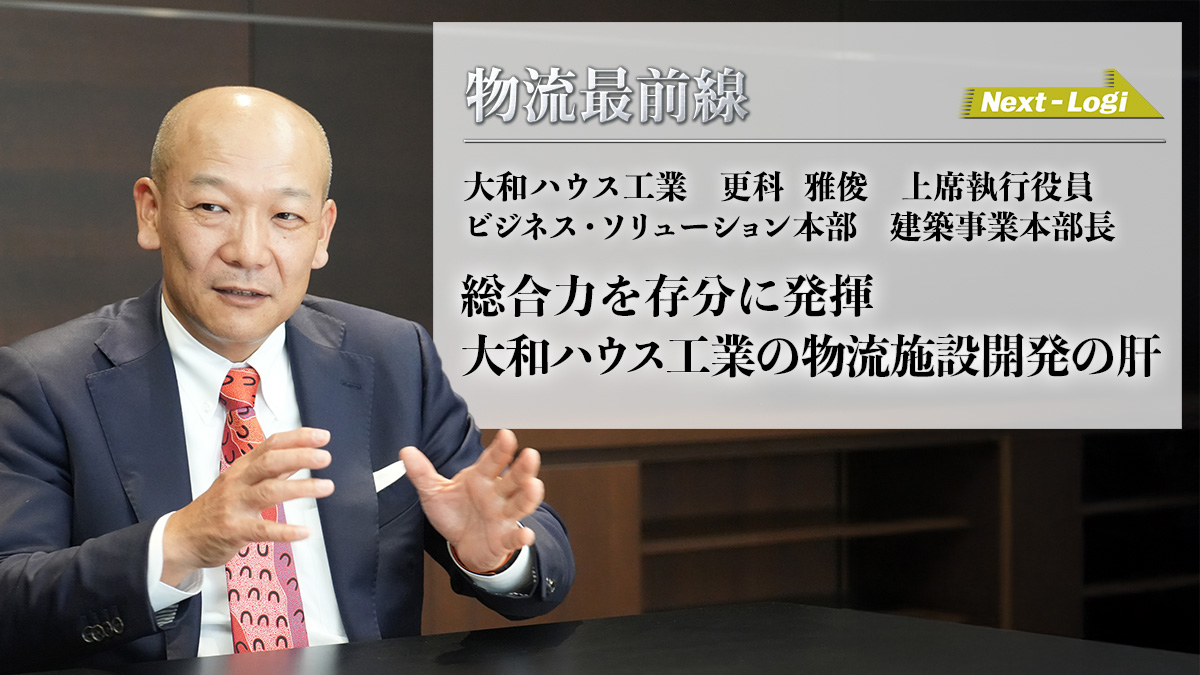1955年創業の住宅メーカー、大和ハウス工業。物流施設では棟数、開発・延床面積ともにトップを占め、ゼネコン、デベロッパーの両面から市場をリードしている。一時の「竣工即満床」から需要は落ち着くも、建築事業本部長、更科 上席執行役員は「時代に合わせ、土地や既存建物の用途を変えたっていい」と今後の展開に柔軟な姿勢を見せる。2024年問題が建設業界にも物流業界にものしかかる今、この荒波を乗り越える術を聞いた。(取材日:2025年3月28日、於:大和ハウス工業東京本社)
関東周辺で物流適地開発は困難
入札には参加せず適地をつくる
―― 御社の物流施設の開発状況から聞かせてください。
更科 当社は1955年の創業以来、製造施設、医療・介護施設、オフィスなどさまざまな事業用建築を手がけ、物流施設も建設してきました。
2002年からは「Dプロジェクト」を開始し、デベロッパー事業も始め、オーダーメイドのBTS型物流施設開発を手がけるようになりました。
実は住宅ではなく、倉庫を建てるところから始まった会社なんです。「建築の工業化」を理念に、プレハブ住宅をつくったり、標準化してシステム建築を行ったり、そこから次は「良い倉庫を建設するには」「自ら倉庫のデベロッパーにもなろう」と広がってきました。
しかしBTS型では「今すぐ入居したい」というニーズに応えられません。そこで2013年、物流施設の新ブランドを「DPL(ディープロジェクト・ロジスティクス)」とし、立地条件の良い場所に、複数テナントが入居できるマルチテナント型の開発を強化する方針を打ち出しました。
<手前からDプロジェクト坂戸、DPL坂戸II、DPL坂戸、DPL坂戸B。4棟が近接する(埼玉県坂戸市)>
<DPL新横浜II(横浜市都筑区)にはジェンダーレストイレも>

―― BTS型とマルチ型の比率や、空室率については。
更科 累積の開発件数はBTS型とマルチ型で5:5ですが、面積で見ると3:7でマルチ型の方が多いです。空室率は、やはり当社でも上がっています。
当社がベンチマークとしているのは、「竣工1年で稼働率50%、2年で満床」。以前は、竣工前に満床となるケースや、竣工1年以内に満床になるケースが多かったのですが、ここ2~3年は供給過多です。ちょうど多数のデベロッパーが参入してきた頃、ベンチマークが崩れてきました。
今のところ竣工1年で50~60%には達しますが、一部では2年で70%ぐらいの施設もあります。満床になるまでに時間がかかるようになっています。
土地代に加えて建設費高騰の影響もあり、他のデベロッパーからは「土地を買ったが、開発できないまま転売した」「入札が不調に終わった」といった話も聞きます。
当社の場合、あまり入札には参加せず、新たに土地を区画整理でつくったりしていますが、どうしても都心部を離れ、圏央道周辺が多くなります。おのずと圏央道エリアでの空室率は高くなってきます。
物流施設デベロッパーにできない
独自のスタンスで魅力度をアップ
―― 九州や中部、東北など地方での物流施設開発に力を入れるのが、御社は早かった印象です。
更科 そうですね。住宅メーカーとして全国津々浦々に事業所があるので、それぞれに営業スタッフや開発スタッフがいます。その点が有利でした。
例えば、工業団地を開発する場合、この区画は工場用地として分譲し工事を請け負う、この区画は当社がデベロッパーとして倉庫を建設し貸し出す、といった複数のアプローチができます。これは物流施設専門のデベロッパーにはできない、当社の強みです。
<フジタと土地区画整理から共同開発したDPL茨木北(大阪府茨木市)>
―― 御社は2013年、建設会社のフジタを子会社化しました。その狙いは。
更科 フジタを子会社にした理由は、元々、ゼネコンとしての技術力に加え、強みであった海外での展開力と国内の区画整理などの開発力が当時の当社には無く、国内外においてのシナジーが見込めるためでした。また、当社の物流施設の建設は、元々は自社で建設していましたが、自社の工事スタッフや技術系スタッフを充ててしまうと、年間の建築棟数には限りがありますから、結局、総数は増えず売上が伸びていきません。
そこで開発物件は他社に依頼し、当社の技術者たちは請負物件に専念できるような方針に変えました。
ただ、建設業界は人手不足だと話したように、潮目は変わっています。フジタがグループに入ったことにより「自分たちでつくる」「フジタにつくってもらう」「複数の建設会社で協力してつくる」など、さまざまな案件を組み合わせ、「つくれない」問題を解決しています。
―― 子会社の中には物流会社もありますね。
更科 大和物流の事業は、大和ハウスグループの建設工事に使用する建設資材を含む、建材に特化した物流をメインとしています。
最近は建材以外の物流業務の受託事業も伸ばしています。今後は、建材を運ぶトラックの特殊性を生かし、売上を伸ばしていけたらと思っています。
―― 2024年問題で「標準化」や「荷待ち時間の短縮」がキーワードになっています。そのあたりの変化は。
更科 マルチ型の物流施設については、建築基準法の制約から、効率的な柱割り、スパンといった視点で決めることが多いので、どう機器を組み合わせて使うかという発想が主になると思います。
バース予約システムの導入は活発ですね。当社は2017年、Hacobuに出資し提携しました。バース予約システムやトラック動態管理システムを、当社の物流施設に標準搭載し入居企業へのサービスレベルを上げようと、いち早く取り組んできました。
―― ダイワロジテックを2012年に設立したのも早かったですね。
更科 ダイワロジテックは、WMSや庫内搬送ロボットなど、さまざまな物流ソリューション開発会社をパートナーとする、物流事業基盤構築会社です。フレームワークスとの出会いが設立のきっかけになりました。
当時、私は営業担当で、テナント企業は物件を探す前に、どのシステムを入れようかと検討するのですね。入居企業や物流事業者のニーズを聞きながら、われわれは空間を提供するだけでなく、ソリューションの提案も必要だと感じました。
それなら当社がシステム開発会社とコラボしてはどうか。出資も含め、いろんな展開が見込めると感じ、参画しました。ダイワロジテックを通じ、この課題にはこの会社のシステムを、この分野ではこの会社のロボットを、と選択して入居検討企業に提案できることは当社のウリです。
2024年問題は物流・建設業界に
大きな変革をもたらしている
―― 昨今話題の2024年問題については、どんな影響がありますか。
更科 当社は住宅メーカーおよび建設会社として荷主の立場でもありますが、今日は物流施設のデベロッパーとしてお答えしますと、今のところ大きな影響は受けていません。
ただ、オペレーションする荷主、物流事業者は、物量や必要なトラック台数などを把握するため奔走していますし、物流施設側としても、システムを導入し支援するようにしています。
建物自体にハード面で大きな変化はないものの、ソフト面では、より支援するようになってきているのが現状です。
トラックドライバーの時間外労働の上限規制により、長距離運転ができなくなり、中継拠点を設ける物流事業者も増えています。その一端で、リーシング面では「在庫を持とう」と聞くようになってきました。これまで一度に運べた物が運べなくなり、「もう1か所、在庫を持てる場所がほしい」といった新たなニーズが出てきています。
今後、中継拠点となる立地に物流施設の開発を求められる話も出てくるでしょうが、今はまだ大きな変化の手前という感じがしています。
―― 人手不足については、いかがですか。
更科 かなり人財を採用しにくい状況です。2024年問題は物流業界にとって大きいことですが、実は、一番大きいのは建設業界です。
建設現場では、残業規制によって、まず単純に工事期間が伸びます。そうすると、建設需給のバランスが悪くなります。
製造業の国内回帰が進み、国内で半導体などの工場建設が増えていますし、40~50年前につくったビルの再開発も進んでいます。災害復興としての建設需要もあります。建設従事者の取り合いになりますよね。
建設の需要と供給のバランスの崩れと、働き方改革が同じタイミングで来てしまった影響は非常に大きいです。
―― 資材の価格高騰や人件費の上昇も、影響が大きそうですね。
更科 どうしても戦争など世界情勢の影響を受けますし、燃料コストや輸送コストもかかります。それがデベロッパーにのしかかり、加えて人手不足、工期の伸び、いろんな課題が重なっています。
おそらく、今後もまだ建設費は上がるでしょう。となると、早く物事を決めて工事をしないと、なかなか物流施設は出来上がってきません。実際、当社の着工件数も減っています。
物流施設はポテンシャル高い建物
時代の変化にも柔軟に対応できる
―― 物流施設の開発に関して、今後の展開は。
更科 物流施設って、突き詰めると、実はいろんな用途に使えるポテンシャルの高い建物だと思います。
そもそも床の荷重が1.5トン、天井高が5.5メートルあったり、免震構造だったりして建物は屈強です。しっかりした躯体の建物をつくっていけば、「事務所や作業所として使いたい」「R&Dとして使いたい」「冷蔵・冷凍倉庫にしたい」など、時代のニーズに合わせて改造してもいいわけです。
有名な一例は、ユニクロの有明本部。もともと6階建ての倉庫だったところを、3フロアは外壁の一部を窓に変え、物流センターとオフィスになりました。
仮想店舗をつくって従業員の研修をしたり、商品陳列やオペレーションのシミュレーションをしたり、使い方はさまざまです。カスタマーセンターを入れたり、従業員の福利厚生でジムや図書館を入れたり、どんどん機能も増えています。
つまり、倉庫はもっといろんな形があっていい。しっかりした建物をつくり、時代に合わせて用途を変えていく、そんな「物流施設との並走」をしていきたいですね。もちろん冷蔵倉庫など、要望を受け用途を絞った施設をつくるケースもありますが、ニーズに合わせて建物の中を転換していくフレキシビリティをメインにしたいと考えています。
データセンターの開発も同じ発想です。元々、物流施設をつくる計画で確保していた土地でも、電力や通信の確保ができると見通せたタイミングで、データセンター用地に変更することがあります。
実際、西東京であった例では、物流施設を開発している途中で「電力もあるしデータセンターとして使いたい」という話をもらい、急きょ図面を分割。土地の半分に物流施設を、もう半分にデータセンターを建てる計画に変更した経験があります。
<千葉県印西市のデータセンター群「DPDC印西パーク」イメージパース>
―― データセンターに注力するデベロッパー、増えていますね。
更科 特にデータセンターは、生成AIが出てきて必要なデータ量が増える一方のため、かなりニーズがあります。
ただ、しっかりした地盤でなければならない、電力が確保できなければならない、など立地条件が厳しく、さらに電力を引くのに5年から10年かかるとなると、物流施設と比べ開発は限定的になります。
今は首都圏と関西圏がほとんどですが、今後、地方でも展開されると思います。当社もこの4月から、建築事業本部から「データセンター事業本部準備室」を独立させ、人員体制を強化しました。
―― 東京湾岸地域の倉庫群の建て替え需要については、どう見ていますか。
更科 30~40年前につくられた冷凍冷蔵倉庫は、かなり古くなっており、注目しています。しかし建て替えるとなると、今ある荷物をどこかに移さないといけないのに、出す所がない状況です。
当社の既存倉庫をうまく使って、そこにいったん荷物を逃がしてもらい、建て替え工事も当社でやらせてもらう、そんなふうにできるとリーズナブルかと思います。その過程で余った資産があれば、当社が買い取ることもできるでしょう。
―― 御社の開発物件数は、急激に増えましたね。
更科 日本ロジスティクスフィールド総合研究所調べによると、国内では当社の物流施設が一番、棟数(約340棟)も総延床面積(1338万m2)も大きく(2024年9月末現在、施工中含む)、シェアは3割ぐらい。デベロッパーとしてはトップです。
―― 2024年度の予算額はどれぐらいでしたか。
更科 物流施設の土地・建物だけで見ると、投資額は年間約2000億円です。分譲用地の開発や海外開発等を含む建築事業領域では「第7次中期経営計画」の5か年で計1兆5000億円の計画を組んでいます。
ここ1~2年の着工棟数は減っていますが、その前は3年かけて年間20棟ぐらい着工しました。今は年間5~6棟なので、4月以降はもう少しペースを上げ、年間10棟以上は着工したいと思っています。
―― 「もう関東圏に物流施設をつくれる土地はない」とよく聞きます。最近は、他のデベロッパーもそうですが、地方での竣工が多いですね。
更科 関東圏での開発は少なくなりましたね。当社は着工が減った分、建物の転換をして新しく付加価値を付けるなど、工夫しています。
それこそ古い建物を冷蔵倉庫に変えたケースや、工場を倉庫に改修したケースもあります。過去に当社がつくった建物は、ある意味財産です。ゼロからつくるだけでなく、改修や増改築も含め有効に使い、当社の事業・商業施設を再生する事業「BIZ LIVNESS(ビズ・リブネス)」の売上を伸ばそうとしています。
「つくった責任」もありますから、未来に向けて磨き直し、世の中に出したい。まだまだやれることは、いっぱいありますね。
例えば、震災時、大型の免震物流施設が、地域の人たちの一時避難所として役立つなど、物流を中心とした地域貢献や街づくりができればと思います。
―― 最後に、LNEWS読者にメッセージをお願いします。
更科 当社は全国で物流施設を開発できる体制にあり、実際、北海道から沖縄まで施設を持っています。これらを物流施設の建て替え時に一時利用してもらうとか、事業環境の変化に伴い、施設を当社が買い取らせてもらい用途を変えて売り出すといったこともできるでしょう。建設会社でありデベロッパーでもある当社のリソースを使えば、お互いに非常にメリットがあると思います。
私も就職したばかりの若い頃は、人が集まる商業施設やビルの仕事がしたいと思っていました。ところが、いざ物流業界に足を突っ込むと、「物流は社会を支える重要なインフラだ。この機能がないと世の中は回らない」と気付かされました。この業界にすごく魅力を感じます。
「物流を人気業界にしたい。一緒に盛り上げたい」という思いで開発に取り組んでいます。多様な要望に応えられる会社だと自負していますので、ぜひあらゆる問題を当社にご相談ください。
取材・執筆 稲福祐子 山内公雄
■プロフィール
更科 雅俊(さらしな・まさとし)
1971年 新潟生まれ
1994年3月 早稲田大学教育学部社会科社会科学専修卒業
1994年4月 大和ハウス工業入社、東京本店 建築事業部に配属
2007年1月 東京本店 建築事業部課長
2013年4月 東京本店 建築事業部副事業部長
2019年3月 東京本店 建築事業部事業部長
2022年4月 執行役員
東京本店長
東京ブロック長兼信越ブロック長
東京本店建築事業部事業部長
建築事業本部営業統括部長(東日本担当)
2024年4月 執行役員 建築事業本部長
2025年4月 上席執行役員 ビジネス・ソリューション本部建築事業本部長(現)
■大和ハウス工業 Webサイト
https://www.daiwahouse.co.jp/
大和ハウス工業/愛知県小牧市に19.2万m2のマルチ型物流施設稼働開始