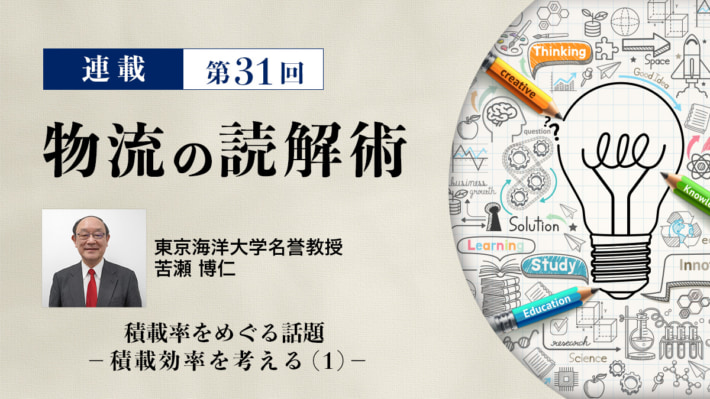積載率を考え直してみよう
物流の効率化を考えるときに、しばしば積載率が話題になる。たとえば、政府の総合物流施策大綱においても、長い間積載率の向上がうたわれてきたが、成果に結びついたとはいいがたい状況にある。
そもそも積載率が低いことには、それなりに原因や理由があるはずだが、その理由を我々が理解していない可能性がある。ひょっとすると、我々が積載率に対して誤解や勘違いをしているのかもしれない。
国土交通省では、積載率の考え方をより発展させて、積載効率(=積載率×実車率)という概念を提示しているが、ここでも積載率が用いられている。そして、現在の積載効率は約40%前後であるが、目標値としての積載効率は日本全体で44%としている。
今回は、「積載効率を考える」の第1回として「積載率」を取り上げ、「人と貨物の違い」「乗用車と貨物車の違い」「積載率とサービスのトレードオフ」について考えてみることにする。
なお、積載率とは「『積載可能量』に対する『実際の積載量』の比率」である。
話題1:人と貨物の違い(一方通行の貨物)
交通や輸送の視点からみたとき、人と物の違いの一つに、「人は往復輸送、物は片道輸送」がある。つまり、人の移動は引っ越しや長期の旅行でない限り、通常は毎日家に戻ってくるので、往復移動になっている。一方で物は、農場や工場で生産された生鮮食品やビールが、消費者が購入して胃袋に収まるように、片道の一方通行が基本である。
このため、仮に出発時の積載率が100%だったとしても、到着後の復路に貨物がなければ積載率は0%となり、往復での積載率の平均は50%になってしまう。もちろん、往復での貨物の確保は運送事業者ならだれもが望むことだが、そもそも貨物の流れが往復で不均衡であれば、仕方のない部分もある。
このため積載率から考えても運送会社の経営からしても、復路も貨物の確保が重要である。
ちなみに、大都市よりも地方都市の路線トラック業者が成長した理由の一つに、「地方の業者は、地元から大都市向けの数量の少ない貨物(往路)を確保するとともに、数量の多い大都市発地元行きの貨物(復路)を容易に集荷できたから」という説があるくらいである。
話題2:乗用車と貨物車の違い(乗車率を気にしない乗用車)
街なかを走っている乗用車は4~5人乗りが多いが、1~2名の乗車が多い。この場合、貨物車の積載率に相当する乗車率は20~40%であるが、乗車率が低いことはあまり話題にならない。かつて、各国でHOV(High Occupancy Vehicle)ということで、複数(通常2~3人)乗車している乗用車を優先通行させる都市交通政策があった。しかし、一部の海外の大都市を除けば定着したとは言いにくい。その背景には、出発時刻の調整、待合せ場所の確保、プライバシーなどの問題もあったとされている。
貨物車については、しばしば積載率が取り上げられる。「空で走ることはムダ」「空いているのにもったいない」などである。もちろん、このようなムダを排除するために、求車求貨システムが利用されているし、荷主も積載率の向上を考えている。この一方で、「積合せならば、積載率を高めて、できるだけ貨物が多いほうが儲かる」が、「1車貸し切りならば料金は同じなので、積載率が低くても貨物が少ないほうが楽」などと思うことは、不謹慎なのだろうか。
話題3:積載率と顧客サービスのトレードオフ
約20年前に、鉄道貨物輸送の技術協力の一員としてある途上国を訪れたとき、鉄道会社の幹部と面会して、運行計画について話し合ったことがある。
私 :この国では定時運行が難しそうですが、今度の貨物鉄道の計画を機に、顧客サービスのためにも定時運行を実施しませんか。
相手:我々は、積載率が低くて利益が少ない状態ならば、定時運行するつもりはありません。積載率が高いほうが利益も大きいのだから、顧客の都合よりも積載率を優先する。あなたには、顧客の都合よりも我々のビジネスのことを考えてほしい。
その国の鉄道会社が独占企業であることをはじめ、トラック輸送に比較して有利な条件がそろっていることも背景にあるが、積載率と顧客サービスのトレードオフを改めて考える機会になった。
このように、積載率も、顧客サービス、営業利益、荷役時間などとともに、ビジネスにおける検討項目の一つのはずである。だからこそ、積載率を最優先にできるかどうかは、それぞれの事情によって変わることになる。
積載効率を読み解こう
積載率については、「貨物の特徴や顧客サービスとのトレードオフを踏まえ、優先順位を考えながらも、できるだけ積載率を高めたほうが良い」ということに落ち着くのだろう。
次回(第32回)以降は、トラック運送における生産性の向上と積載効率について、読み解いていこうと思う。
参考文献
1) 物流効率化法ポータルサイト
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/faq/♯sekisai_koritsu
2) 国土交通省:物流を取り巻く動向について、2020年7月
https://www.mlit.go.jp/common/001354692.pdf
連載 物流の読解術 第30回:物流の効率化のための検討項目 -効率化を考える(9)-