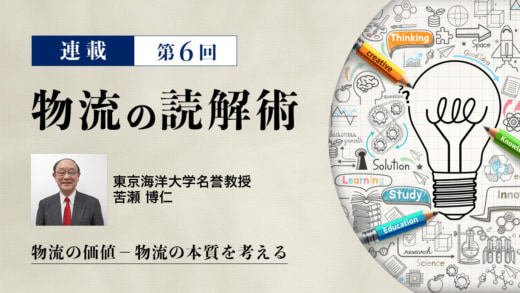輸送(空間の移動)による価値の向上
物流では、「物を運ぶ(輸送)」行為や「物を預かる(保管)」行為に、料金を支払うものである。だから、運んでもらったからと言って、貨物が物流事業者の持ち物になるわけでは無い。つまり、貨物の所有権が移転することは無いのである。
輸送は、「生産場所と消費場所の距離差」を埋めるものである。つまり、輸送は「空間を移動すること」で商品や物資の価値を高めている。荷主企業からみれば、「生産地点で仕入れて、輸送し、消費地点で販売する」ということになる。
たとえば、地方で生産された農産物を都市の消費者に販売するためには、輸送しなければならない。よって、「輸送があってこそ商品の価値が生まれる」ということになる。
保管(時間の移動)による価値の向上
保管は、「生産時点と消費時点の時間差」を埋めるものである。つまり、保管は「時間を移動すること」で、商品や物資の価値を高めている。荷主企業からみれば、「仕入れないし生産できる時期に購入し生産し、それを保管して、消費する時期に販売する」ということになる。
たとえば、収穫時期に輸入した原材料(例、小麦)を、通年の販売に合わせて保管することは、「生産のピークと通年の販売の時間調整」である。また、クリスマス用アイスケーキをあらかじめ製造して保管し、クリスマスの時期に一挙に販売することは、「販売のピークと生産の平準化の時間調整」である。
流通加工・包装・荷役による価値の向上
流通加工・包装・荷役は、「商品を組み合わせるセット化」「品質維持のための包装」「輸送や保管に付随する積みおろしの作業」などにより、商品の価値を高めるものである。
流通加工は、キャベツ1個が200円のとき半分にカットして110円で販売するように、商品の小分けや組み合わせによって、価値を高めている。
包装は、段ボールなどで商品を保護するとともに、ギフト包装やリボン掛けなどで商品の価値を高めている。
荷役は、商品や物資は、人と違って自ら移動できないからこそ、積込み荷おろしなどが必要になる。もしも台車やフォークリフトがなければ、荷役作業にも多くの時間がかかってしまう。
商品の価値と、物流の価値
いくら優れた製品を生産できても、いくら良い商品を仕入れたとしても、それらを消費者の望む時期や状態で届けることができなければ、消費者にとっての価値はない。
たとえば、消費者が自動販売機で温かい缶コーヒーや冷たい飲料水を購入することは、「飲みたいとき、飲みたい温度で、自ら運ぶことも保管することもなく、ただちに飲める状態の実現」でもある。もしもスーパーマーケットに買いに行けば、同じ商品でもより安価かもしれないが、買いに行く手間と時間を省きたい。まして、美味しい水道水を水筒に入れて持ち歩けば相当安いに違いないが、重たくてかさばるのを嫌がり、ついつい飲みたいときに出先で購入してしまう。このことは、自動販売機までの輸送や一定の温度での保管という「物流の価値と便利さ」に対して、対価を支払っていることでもある。
つまり、消費者は、商品の価値もさることながら、「望ましい状態を実現する物流の価値」も高く評価していると思えるのである。
<物流の価値>
輸送(空間の移動):生産場所と消費場所の距離差を埋め、価値を高める
保管(時間の移動):生産場所と消費場所の時間差を埋め、価値を高める
付加価値の向上 :流通加工・包装などで、商品の価値を高める
(第1回~第6回、以上)