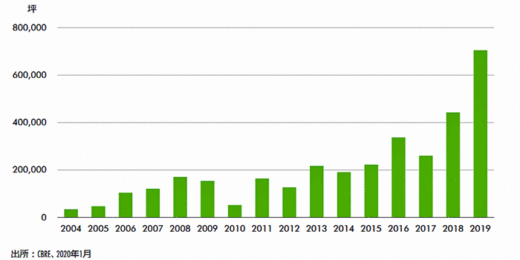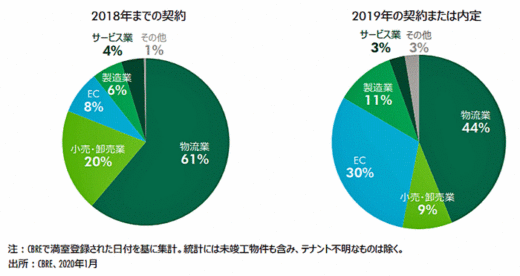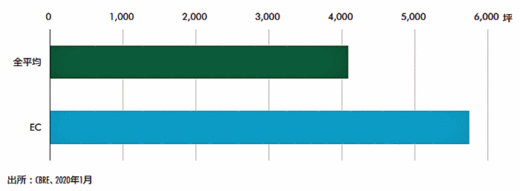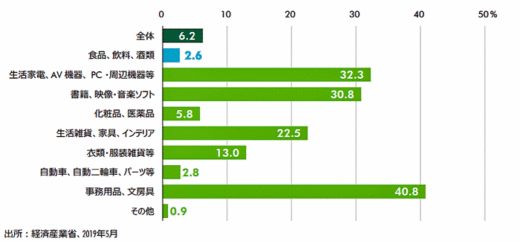CBREは4月14日、「ロジスティクス マーケット – 首都圏の物流需要を牽引するeコマース」を発表した。
リサーチは高橋加寿子シニアディレクター。
それによると、2019年は、物流施設の需要が大きく伸びた年となった。首都圏大型マルチテナント型物流施設(LMT=Large Multi-Tenant Properties) の新規需要は、2019年は年間70万坪を超えた。これは、2018年の新規需要の1.6倍にあたる。
さらに、未竣工の物件でもテナントの内定が進んでいる。2020年に竣工予定の首都圏LMT43万坪のうち、入居テナントが決定または内定した面積は49.7%と、約半数に達している (2019年Q4時点、CBRE調べ)。このように、物流需要は過去最大の盛り上がりを見せていると言っていい。
物流施設の需要の牽引役として、足元では特にeコマースの存在感が際立っている。CBREは2020年1月時点で首都圏LMTの契約・内定テナントを調べた。それによると、2018年までの契約テナントは、物流業(3PL)が61%と体制を占めている。続いて小売・卸売業の20%が続き、eコマースは8%であった。物流機能のアウトソーシングの流れを取り込んだ3PLが、従来は物流需要の主役だったといえる。
一方、2019年中の契約または内定テナントを見ると、eコマースの占める割合が30%に大きく増えた。物流業の割合は44%と依然としてシェアがもっとも高いものの、需要の主役はeコマースに移りつつあるといえよう。
eコマースの契約を詳しく見てみると、1件当たりの契約規模が大きいことがわかる。全テナントの1件当たりの平均契約面積約4100坪に対して、eコマースは約5700坪。全体平均より40%ほど規模が大きい。また、2019年中の契約(内定)に限ってみると、約6200坪でさらに大きくなっていた。
そして、eコマースでの物流施設の規模が大きい理由を2つあるとしている。
店舗を持たないeコマースは、物流センター設備に積極的に投資することが一つ目の理由だ。Webサイトの使いやすさのみならず、物流センターの出荷能力と宅配網もまた、売上に直結するからである。
もう一つの理由として、倉庫内の機械化・自動化が挙げられる。eコマースの物流センターでは、多種多様な個人の注文品をピックアップし、梱包しなければならないため、多くの人手を必要とする。人材の確保がますます困難になるなか、ロボットなどの最新テクノロジーを導入することが急務となっている。
そしてこのようなテクノロジーの導入には、一定規模以上の規模が必要とされる。規模の大きい施設をなるべくコストをかけずに書くするという意味では、都心から距離のある立地の施設も、一定程度の需要があると考えられる。実際圏央道エリアにおけるeコマースの平均契約面積は8000坪を超えている。
一方で、東京ベイエリアでのeコマースの平均契約面積は約2300坪。ここで想定されるのは、ラストマイル配送のための小拠点需要である。賃料水準の高いこのエリアの倉庫は、多種多様な在庫を大量に保管するのではなく、出荷頻度の高い一部の商品保管や、最終配送地に向かう荷物の積み替えが主な使われ方と考えられる。
その中には、鮮度や温度管理が重要であるため配送時間が短いことが望ましい食品類のストックも含まれるだろう。ところで、食品類のEC化率は2.6%で、全体の6.2%と比べてまだ低く、今後の拡大余地が大きい。この分野がさらに拡大することで、都心の住宅地に近い立地についても、eコマースの物流拠点としてのニーズがますますたかまるだろう。
最後に、COVID-19感染拡大防止対策で外出が控えられる昨今、eコマースの利用率や食品分野などの利用範囲の拡大が促進され、物流施設ニーズはさらに押し上げられるだろう。求められる面積は首都圏の内側と外側で大きく異なるものの、eコマースはそのいずれにおいても今後しばらく物流需要を牽引していくだろう、と結んでいる。
阪急阪神HD/豪州で特定子会社が物流不動産賃貸・開発事業開始