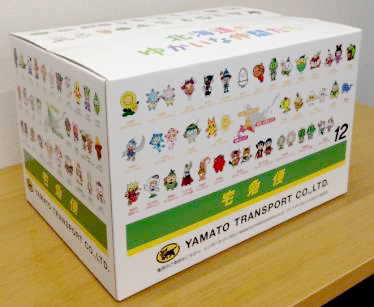北海道とヤマト運輸は6月5日、物流・人流の活性化や観光支援など、地域社会の活性化と道民サービスの向上を目的に「包括連携協定」を締結したと発表した。
<2015年12月オープンのイオンモール旭川駅前店の一括免税カウンター>

<写真左よりヤマト運輸キャラクターシロネコ、北海道総合政策部黒田敏之交通企画監、北海道の高橋はるみ知事、ヤマト運輸の長尾裕社長、ヤマト運輸松井克弘執行役員北海道支社長、ヤマト運輸キャラクタークロネコ>

北海道とヤマト運輸の連携事項は9分野にわたり、物流・人流の活性化に関することでは、「共同輸送の推進」「近距離輸送サービスの創造」を挙げている。
このうち、共同輸送の推進は、トラックなどの輸送において長距離かつ積載効率の低下が課題となっている地域で、他の物流事業者と連携し、1台のトラックに複数の物流事業者の荷物を積載する共同輸送に取組み、持続可能なサプライチェーンの構築を目指す。
例えば道北エリアへの納品物流を行っている事業者と協業することで地域に向かう車両を減らすなど、物流効率化について課題を抱える地域や事業者と連携しながら、共同輸送を展開していく。
近距離輸送サービスの創造では、過疎化や高齢化が進む地域において、生活必需品の買物や公共交通機関の維持に課題を抱える中、ヤマト運輸は道内7社の路線バス事業者と連携し、12路線で客貨混載を展開している。
2018年2月には、士別市内から士別朝日地区まで路線バスで生活必需品を輸送し、ヤマト運輸が買物便として士別朝日地区に住ンでいる顧客に届けるスキームについてトライアルを行った。
今後、同地域での持続的なサービス提供を目指すとともに、同様の課題を抱える他の地域でも、地域パートナーと連携し、買物便のサービスを拡充するなど新たな価値の創出に取り組む。
また、安全・安心な地域づくりに関することでは、「道政広報・魅力発信に関すること」「観光支援や道産品の販路拡大に関すること」「災害対策に関すること」「環境維持・保全に関すること」「地域の福祉に関すること」「北海道の人財育成に関すること」「その他、北海道の活性化に関すること」を挙げている。
ヤマト運輸、奥尻町/客貨混載型の公共ライドシェアの実証運行開始