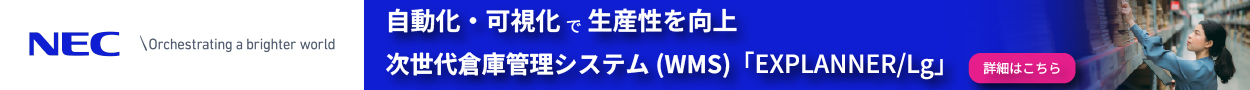プロロジスは3月21日、米国本社からハミード R.モガダム共同創業者会長兼CEOを迎え、日本法人の山田 御酒 会長兼CEOと2人での記者会見を行った。モガダムCEOは来年1月に退任を発表しているが、それをふまえ改めて取材陣にグローバル市場や今後の市況予測について持論を語った。
モガダム会長はグローバル市場について、運用資産が30.8兆円、世界20か国において、約1億1200万m2の物流施設を開発していることなどを説明。世界のGDPに占める割合は2.8%、同社が事業を行う国に限れば4.0%にも上る。そのうえで現在のプロロジスについて、「創業地のアメリカ合衆国だけでなく、ヨーロッパやアジアでも最大規模のデベロッパーである」と強調。まだ開発余力があることをアピールした。
アジア地域の展開は、日本・インド・中国・シンガポールなどをキーマーケットとして挙げ、特に日本に関して、「技術力が素晴らしくイノベーションに富んでいる」と評価。他方で、中国を大きな経済大国であるとしたうえで、「現在落ち込んでいる中国経済の下振れは底打ちに入っており、あとは上がるだけ」という分析を行った。
物流不動産における世界的なトレンドとして、消費拡大の一方、倉庫開発の供給が頭打ちになり、参入障壁が高まっていると説明。サプライチェーンコストでは輸送費が高い割合を占めることから、消費地に近い立地を選ぶことで輸送費を1%削減できれば、顧客が負担する賃料を17%引き上げても成り立つ、という持論を語った。
日本でもこのロジックが成り立つとして見ているが、「労務費の上昇圧力があることから、輸送費削減をそのまま顧客への賃料増へ転換することは難しい」としており、ある程度は輸送事業者の労務費へと転換されるだろうという見解を示した。
次世代に向けた取り組みとしては、未来の物流を担う50以上のイノベーション企業への投資を行っており、実績額は2.5億ドルとなっている。またネット・ゼロ目標から太陽光発電の導入、転じて物流施設のデータセンターへの転用にも言及。Google、メタなどのハイパースケーラーが求める広大な土地、細かな指示書に沿った設計、機材の事前調達ができることの競争優位性、さらには約120人体制でのエネルギー部など独自の強みを述べた。
日本法人 山田 御酒 会長兼CEOが、国内市場について解説。現在国内では87施設、約614万m2の施設を開発・運営しており、関東首都圏が50%、近年は従来開発を活発に行っていなかった東北地域などで開発を進めている実績を振り返った。なお開発の方向性については、都市型物流施設が地方のマルチ型物流施設と建設コストがあまり変わらない点から、地方の中核都市でマルチ型施設の展開を進める判断を行った結果だという。
新規供給が抑制されている現状については、建設の高騰を原因としており、2021年を境に熊本・北海道を中心とした半導体工場の建設が一挙に始まったことや、大阪・関西万博の準備に伴い建設工事が関西に集中したこと、全国各地でのデータセンターの開発、東京を中心とした大型の再開発などの要因を挙げた。
立地戦略と施設開発では、BTS型・マルチテナント型・都市型の3基軸で展開。今後はロボット導入なども視野に入れており、自動フォークリフトやAGV等の縦移動を可能にするエレベーター自動連係システムの実装、電力需要が上がっていることへの対応として特別高圧受電などを盛り込んだ物流施設の開発を進めている。
近年では顧客の需要に応えHAZMAT(危険物倉庫)も展開。プロロジスパーク古河6を例に、竣工前に満床になった実績から次のプロロジスパーク古河7を開発中であることに触れ、来年2月の竣工前に多くの問い合わせを受けていることを明かした。「昨今コンプライアンスが厳しくなる中、顧客もグレーだった荷物を安全なところへ置きたい、という声が増えてきた。具体的には、化粧品やアルコール、スプレー類のほか、バッテリーの大量保管といった需要が増加している」といった、顧客ニーズの変化についても述べた。
地方中核都市を中心とした2024年問題に対応する拠点整備について、岡山、東海、郡山、盛岡など、物流の中継地点としての機能をもつ物流施設の開発を進めており、多くの利用者から関心を集めているという。
そのほか、顧客の課題に寄り添うソリューションとして、物流課題のコンサルティングにも注力している。「コンサル業務については当初不安だったが、実際にやってみると意外に多くの問い合わせをいただいた」と語り、3PLをはじめ物流会社や製造メーカー、小売などにサービス提供を行った。さらに支援テーマという観点では、アセスメント・計画や業務改善、自動化導入、サブスクリプションへのアドバイザリーなど多岐にわたっている。
<会見後、握手を交わすハミード R. モガダム 会長兼CEOと、日本法人 山田 御酒 会長兼CEO>

モガダム会長は、2026年1月のCEO退任に際し、もっとも心に残った仕事を問われると「もし子供がたくさんいたら、その中で誰が一番か、と答えなければならないくらいに、とても答えるのが難しい質問。ただ思い返すと真っ先に浮かぶのは日本のプロジェクトで、複雑かつ大規模で技術力を駆使した素晴らしいものだったと思う。経験したプロロジスとしての歩みの中でのイベントであれば、リートの発足を挙げたい」と答えた。
日本法人 山田会長は、今後の物流業界の見通しについて「現状デベロッパーが80社を超える状況はやや異様であり、これは元々オフィスや住宅を建てていた業者が安定を求めて物流施設に着手しているためで、今後もこういった状況が続くわけではない」とし、続けて「マーケット需給の影響もある中、建設費が上がった昨今では金利面などで投資家の利回り目線も上がり、デベロッパーにとってマイナスになりつつある。賃料の上昇で即座に利益を出すことは難しいので、マーケットから離脱するデベロッパーも出てくることから、今後は安定していくだろう」と展望を述べた。また「空室率が10%から4%程度に下がるには3年ほどかかると想定している。2027年ほどまでは大手ゼネコンも手一杯な状況が予想されるので、それを過ぎれば以前の状況に近づきリスタートが切れる」とし、「20年以上毎年コンスタントに供給を続けてきたので、いずれにせよ近況が変わってもやることは同じ」であると語った。
プロロジス/来年1月にCEO交代を発表、新CEOにダン・レター氏