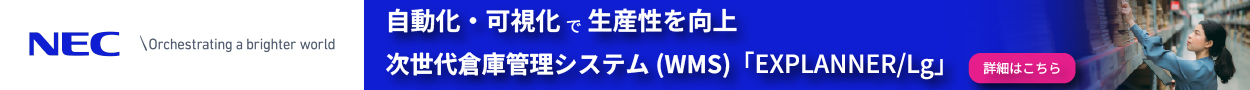国土交通省は、昨年5月に公布された物流関連二法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律、以下「改正法」)について、今年4月からの施行に向け2月18日、事業者が取り組むべき措置についての判断基準と基本方針が示された。
まず改正法の施行規則において、省令の一部を改正し「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法を定めた。それによると荷待ち時間の算定は、運転者が集荷もしくは配達を行うべき場所、またはその周辺の場所に到着した時刻から、荷役等を開始した時刻までの時間、(荷主等の都合により待機した時間に限る)となる。
荷役等時間については、貨物の検品、荷造り、搬出、搬入、保管、仕分けまたは陳列、ラベルの貼り付けなど運転者が荷役等を開始した時間から終了した時刻までの時間とする。
そのうえで、改正後、運送事業者等が取り組むべき事項として「運送者一人あたりの1回ごとの貨物の重量の増加を計画的かつ効果的に実施すること」を原則とし、運送や荷役等について判断基準を示している。
また荷主が取り組むべき事項に対しても判断基準を定める命令が示され、実効性を確保するための取組に関して、責任者の選定と必要な体制の整備を行うことで「運転者の荷待ち時間等及び運転者一人当たりの1回の運送ごとの貨物の重量の状況と、効率化のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること」などが求められる。
基本方針では、物流効率化に向けサプライチェーン全体の関係者が連携を図り、取組効果を一層高めるとともに、環境負荷低減を目指す。そのうえで、改正法に基づく枠組みの活用により、荷待ち時間等の短縮や、運転手一人当たりの運送量の増加を図る取組を推進する。具体的には令和10年度までに全国の貨物自動車による輸送のうち、5割の運行で荷待ち時間を短縮することで、運転者一人当たりの荷待ち時間を年間125時間短縮する。
これをふまえ、荷主等に対し1回の受け渡しごとの荷待ち時間等について、原則として「目標を1時間以内」と設定。また運転者一人当たりの1回の運送ごとの貨物量については、近年40%で推移している積載効率を、全体の車両で44%への増加を実現するものとする。
■詳しくはトラックニュースを参照
・改正物流法/「荷待ち時間」「荷役等時間」の算定方法を省令で規定
・改正物流法/2028年度、荷待ち時間年間125時間短縮を目標として規定